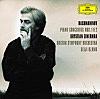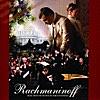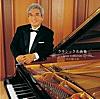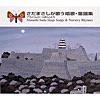「私」が秋に聴きたい音楽。〈その②〉
ようこそ!ブーです。
前回に引き続き、今回も「私」が秋に聴きたい音楽を紹介します!
〈その①〉も見てね。↓
セルゲイ・ラフマニノフ
ラフマニノフはロシア出身の作曲家として有名ですが、その他にもピアニスト・指揮者としても功績が残る音楽活動をしていました。
彼の曲は、聖歌や民謡などの響きに似せた重厚でロマンティックな和音を使っていたり、他の演奏者が嫌がるくらい音から音への幅が広くダイナミックな和音を使っています。
それは、ラフマニノフ自身の手が大きかった為、「同じ音を使った和音」でも順番を変えて幅広く演奏できたからです。

ダイナミックな和音を使っているからと言って大味な曲を作っていたわけではなく、「ピアノ協奏曲 第2番」や「ヴォカリーズ」などは繊細さが際立っています。
この2つの作品は、メロディをより際立たせるために普段は豊かな響き(ハーモニー)を生み出す音の密度や演奏楽器などが減らしてあり、その洗練された繊細で切ないメロディは聴いていて神聖さや神々しささえ感じます。
ラフマニノフ自身も『私はただ、自分の中で聴こえている音楽をできるだけ自然に紙の上に書きつけるだけ』と語っているので、曲を聴くことでラフマニノフという人物の繊細な一面を垣間見ることができます。
「ピアノ協奏曲 第2番」は全3楽章で構成されています。
演奏は3曲合わせて35分ほどです。
第1楽章ではロシアらしい荘厳で重々しい響き、第2楽章では静かな湖畔をゆっくりと歩くような瑞々しさを感じ、第3楽章はフィナーレに相応しい華やかな印象の他に1楽章と2楽章の主要なモチーフ(模範にしたメロディ)が散りばめられています。
3曲とも違った良さがありとても素晴らしい作品ですが、秋の感傷に浸りたいときには無性に第2楽章が聴きたくなるんですよね。
上ではピアノ独奏を紹介しましたが、元々「ヴォカリーズ」という曲は声楽のために書かれた歌曲です。
歌曲と言っても、本来「ヴォカリーズ」という言葉の意味が、『A、あ U、う…』などの母音を使って歌うことや明確な発音の歌詞がない曲を指すので、この曲にも歌詞がありません。
このことから他の楽器のために編曲するには都合がよく、また人気のある曲のため多く編曲がされている作品です。
こちらでも紹介しました。↓
歌ありも良いのですが、より響きが統一されているように感じるので、秋に聴きたいのはピアノ独奏ヴァージョンなんですよね。
エリック・サティ
フランスの作曲家であるサティの作品は〈家具の音楽〉と呼ばれていました。
『家具のように部屋の中に自然と溶け込んでいる』ということで、BGMの先駆けとも言われています。
ゆったりとした曲調でフランスの作曲家らしいアンニュイな雰囲気を醸し出す「3つのジムノペディ」や、愛をテーマにした情熱的でありつつも少し切ないメロディの「ジュ・トゥ・ヴー」などは読書用のBGMとして最適です。
何といっても『家具のような音楽』なのですから、耳に心地好い音量で聴く分には読書の邪魔をするようなことがないのは当たり前か!と1人で納得してしまったブーなのでした。(笑)
ジムノペディはこちらでも紹介しました。↓
私の勝手な意見ですが、サティの作品はフランスという国のアンニュイな雰囲気そのものを表したような独特のテンポと響き、そして揺らぎをもっているので「秋」という季節を強く感じるんですよね。
「Autumn Leaves/枯葉」
元々シャンソンの代表曲と言われている「枯葉」は、今ではジャズのスタンダードナンバー(定番曲)としても有名です。
大変人気があるためシャンソンやジャズに限らず、色々なジャンルのアーティストさんがカヴァーしており、ご存知の方も多いのではないでしょうか?
私が好きなアレンジは、ジャズピアニストのビル・エヴァンスが組んでいたトリオの演奏です。
基になったシャンソンには歌詞があり、『夏に過ごした恋人達の甘い思い出を、冬に向かっていく秋の冷たい北風が運び去っていってしまう』という内容で、恋人達の別れを切なく歌っています。
(細かい紹介はしませんが、聴き馴染みがありシャンソンらしさが1番出ているのは、フランスのシャンソン歌手エディット・ピアフの歌です。)
オリジナルである歌のヴァージョンとは違い、ジャズで演奏されるときには切なさよりも軽快さが生まれます。
そのため、同じ曲でも聴いていて別れを想像させるような重苦しい気持ちにはならず、温かいコーヒーでも飲みながら紅葉を眺めたり、ドライブに行くときにかけたりと、とにかく「秋」という季節を満喫したいときに聴きたくなる1曲です。
交響曲 第5番 第4楽章 アダージェット(マーラー)
グスタフ・マーラーはオーストリア出身の作曲家ですが、『私は3重の意味で故郷がない人間だ。オーストリア人の間ではボヘミア人、ドイツ人の間ではオーストリア人、そして全世界の国民の間ではユダヤ人として…』と語っています。
要は「どこに行っても余所者扱いされる」ということです。
この言葉だけでも十分にツライ人生が想像できますが、このこと以外にもマーラーを精神的に蝕んでいたものがありました。
幼い頃に受けた父親からの暴力や幼少期に亡くなった兄弟達のこと、自分自身の病気、年の離れた妻からの愛が信じられず疑心暗鬼に陥ったり、そして執着と言っても良いほど愛した母の死によって、「愛」という感情に対してナーバスになっていたのです。
そんな愛に飢えて人生の悲しみをたっぷりと抱えていたマーラーだからこそ作曲できたのが、この「交響曲 第5番 第4楽章 アダージェット」別名「愛の楽章」と言われています。
第4楽章だけでも11分~13分程度と長い曲ですが、よかったら聴いてみてください。
自然とため息が出るほどに美しい曲なので、秋の夕暮れ時や月明かりを眺めながら感傷に浸りたいときに聴きたくなります。
タイスの瞑想曲(マスネ)
フランスの作曲家ジュール・マスネの書いた「タイスの瞑想曲」は、憂鬱なときに聴きたい曲としても紹介しました。↓
ゆっくりと紡がれる甘美で官能的な響きと、ヴァイオリンが高音で奏でる切なさで胸が張り裂けそうなメロディは秋の物悲しい雰囲気にもよく合います。
元々はオペラの曲目の1つなのでオーケストラのために作曲されていますが、人気の曲なのでヴァイオリンのソロコンサートなどではピアノ伴奏に編曲され演奏することが多いです。
秋じゃなかったら編曲されたものでも普通に聴くのですが、オーケストラの方が音に重厚感や深みが出るため、私が秋に聴きたいのはオーケストラ演奏のオリジナルヴァージョンです。
「カヴァティーナ」
「カヴァティーナ」は1978年公開の“ディア・ハンター The Deer Hunter”という映画のテーマ音楽です。
この映画は、ベトナム戦争での過酷な体験が原因で心身共に深く傷を負った《アメリカの若き3人のベトナム帰還兵達》の生と死や、彼らと仲間たちの友情を描いています。
ギターが奏でる哀愁のメロディと、それに寄り添うオーケストラやフルートの響きがさらに切なさを演出します。
月の綺麗なこの季節の夜にこの曲を聴くと、センチメンタルな気持ちになって涙が止まりません。
「大人」だからこそ、秋をテーマにした童謡を聴いてほしい。
日本では「ちいさい秋みつけた」「紅葉」「夕焼け小焼け」「まっかな秋」「里の秋」「虫のこえ」…など、秋をテーマにした童謡が数多く存在していますよね。
子ども達にもわかり易いように作られている童謡は、お店のBGMなどでかかっているのを聴くと、大人でも『あぁ…秋だな。』という風に、季節の移り変わりを感じるのではないでしょうか?

そんな秋の童謡の中で特に私が好きなのは「小さい秋みつけた」です。
子どもに聴かせたり歌わせたりするには些かメロディが切な過ぎるように感じますが、秋の物悲しい雰囲気そのものを表している名曲だと思います。
この曲を聴くと、なぜか子どもの頃に感じていた秋の雰囲気や匂い、感情まで甦ってくる気がします。
丸くて大きなどんぐりやイガから顔を出した栗が地面に落ちているだけでワクワクしたり、柿の実がカラスに食べられているのを見て『カラスも柿の色を見て、美味しい時期がわかるんだな…』と無駄に感心したり、落ち葉が水に濡れて土になる前の何ともいえない匂いを感じたり、秋の夕暮れの美しさに胸が熱くなったりと、子どもの頃は純粋に季節を楽しんでいたなとしみじみ感じるんですよね。
なので大人になった今、ひとときだけでも秋という季節の楽しさを思い出させてくれる童謡を聴いて欲しいと思うのでした。